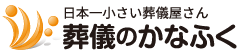キリスト教のイースター(復活祭)とは? 春に巡る”いのち”の奇跡
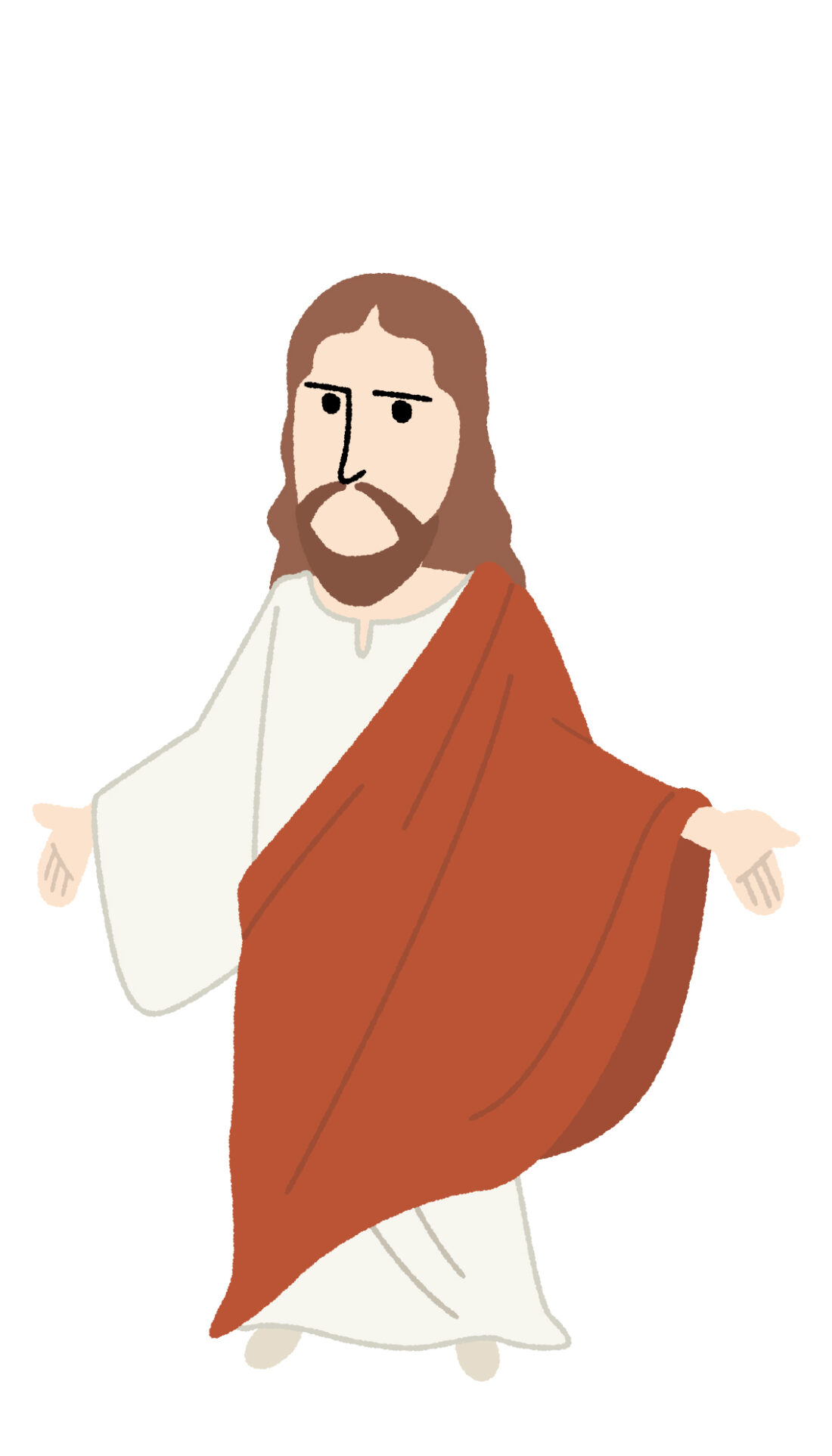
皆様こんにちは![]() かなふく鈴木です。
かなふく鈴木です。
みなさん「イースター(復活祭)」ってご存じでしょうか?
イースターとは、イエス・キリストが十字架に架けられて亡くなったあと、3日目に復活した奇跡を祝う日のことです。
キリスト教の地域では、クリスマスやハロウィンよりも大切にされていると言われています![]()
今回は、日本ではまだあまりなじみのないイースターについて、ぼくなりの視点でご紹介してみたいと思います。
イースターとは、イエスの復活を祝う日
イースターとは、イエスの復活を祝う日のことですが、まずはこの「復活」について、基本的な知識について押さえておきましょう![]()
イエス・キリストは、十字架で処刑されたあと、3日目に復活したとされています。
聖書には、ゴルゴタの丘で磔刑にされた3日後、女たちが墓をたずねていくと、墓が空になっており、天使がイエスの復活を告げたと記されているのです。
また、亡くなったあとに復活するのは、イエスだけでなく、善人も悪人も、最後の審判の日には全ての人が復活するとされています。
イエスの復活は、「死の克服」であり、「永遠の命の約束」であるとも言えます。
このような希望が信者に示され、それをお祝いするのがイースターなのです。
イエスは本当に復活したの?
さて、亡くなった人が、死後に復活するだなんてことが、本当にあるのでしょうか![]()
キリスト教においては、イエスの復活は教えの核心そのものです。
パウロという人物も書簡の中でこう語っています。
「もしキリストが復活しなかったのなら、私たちの宣教はむなしく、あなたがたの信仰もむなしい。」(コリント人への手紙 第一 15章14節)
現代日本に生きるぼくたちからすると、亡くなった人が復活するのは現実的じゃないですよね。
でも、現実的ではない奇跡を起こしたからこそ、イエスは神の子と成り得たとも言えますし、神のなせる業だからこそ、ぼくたち人間には理解が追いつかず、それを「信じるか信じないか」という態度が求められるのだと思います。
ぼく自身は、あるいは地球上のすべての人間は、「イエスが本当に復活したか」を実証することはできないでしょう。
でも、弟子たちが「復活した」と信じ、それによって人生が、世界が大きく変わっていったという事実。それだけでも、イエスの復活には「たしかさ」が宿っていると思います。

イースターは春の行事
イースターは春に行われますが、その日付は年によって変わります。
なぜなら、基本的に「春分の日の後の最初の満月の次の日曜日」に祝われるためです。
つまり、最も早いと3月22日、最も遅いと4月25日になります。
2025年のイースターは【4月20日(日)】です。過去数年のイースター日程は以下の通りです。
- 2022年:4月17日(日)
- 2023年:4月9日(日)
- 2024年:3月31日(日)
- 2025年:4月20日(日)
ヨーロッパやアメリカなどのキリスト教圏では、イースター前の金曜からイースター翌日の月曜までをイースター休暇とするケースが多いようです![]()
カーニバルは、身を慎む前の大騒ぎ
キリスト教の国では、あちこちで「カーニバル(謝肉祭)」が行われます。
有名なところでいくと、ブラジルの「リオのカーニバル」がありますが、このカーニバルとイースターには深いかかわりがあります。
というのも、カーニバルって、イースターの46日前に始まる「四旬節」の直前に行われるお祭りです。
四旬節とは、イエスの受難と復活を思い、節制・断食・祈りをする期間で、これを経て、春の復活祭を迎えます。
四旬節の46日間は身を慎むべきとされていて、カーニバルはその前に「食べて・飲んで・歌って・踊って」楽しむ、いわば、節制前の最後のごちそうや大騒ぎが許された日なのです。

イースターエッグとウサギの意味
ぼくも今回はじめて知ったのですが、イースターには「卵」や「うさぎ」が登場するのだそうです![]()
海外では、カラフルにペイントされた「イースターエッグ」を探す「エッグハント」という遊びが定番で、大人も子どももワクワクする春のイベントなんだとか。ペイントも、卵探しも、どっちも楽しそうですよね![]()
卵やうさぎが用いられているのは、宗教的な由来というよりも、春の自然といのちの象徴として、長く親しまれてきたもののようです。
つまり、卵は「命のはじまり」。殻の中に命が宿り、ある日パリンと割れて、新しい世界へと誕生する、イエスの復活を象徴しています。
そして、ウサギは「多産」の象徴。春にたくさんの命が芽吹くことと重ねて、子どもたちにも親しみやすい存在になっています。
記念日があることの大切さ
イースターのように、毎年やってくる「記念日」があるって、やっぱり大事なことだと思うんです。
毎年その日が来るから、忘れない。忘れずに思い出すことで、心の中に生き続ける。
これは、キリスト教やイエスだけではないですよね![]()
日本の神社やお寺で、毎年同じ時期に同じ行事をして神仏に祈ったり、故人さまやご先祖さまの命日に法事を営んだり。
それに、記念日が1年の中に点在しているからこそ、ぼくたちの暮らしにも「リズム」が生まれます![]()
お祝いの日があって、静かに内省する日があって、その繰り返しが、人生にハリとゆるみをもたらしてくれる。
たとえば、カーニバルとイースター。
カーニバルは思いっきり楽しむ“ハレ”の日。イースターは心を整えて迎える“ケ”の日。
この「緩和」と「緊張」のバランスは、実は世界中の文化にも共通して見られるリズムなんですよね。
人って、ずっと張りつめていられないし、ずっとゆるんでもいられない。
だからこそ、季節の節目や記念日を通して、自分を整えていくことが、きっと大切なんだと思います![]()

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
葬儀や仏事に関するご相談があれば、どうぞお気軽にお問い合わせください![]()
葬儀のかなふく 株式会社神奈川福祉葬祭
代表取締役 鈴木 隆